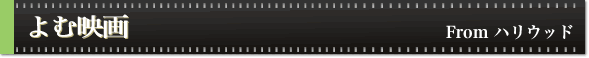|
TEXT BY フィーチャープレス 岩下慶一
|
|
|
『ニューオリンズ・トライアル』を3倍楽しむ法
|
恋愛から戦争、ニューヨークの街角から宇宙まで、ハリウッド映画が扱うテーマ、舞台はそれこそ千差万別だが、そんなカテゴリーの一つにいわゆる「法廷モノ」がある。裁判所を舞台に、そこでの駆け引きや人間ドラマを描いた作品だが、ビデオ屋さんよってはCourt Drama(裁判所モノ)というセクションを作っているところもある位、一つの分野として立派に確立されている。日本映画ではこの手の作品は殆どないのに、何で法廷ドラマがこんなにもアメリカ人を惹きつけるだろう?
|
|
|
| 裁判所に馴染みの薄い日本人にはあまりピンとこない話だが、自己主張がある意味で美徳とされるアメリカでは、コート(court=裁判所)は日常的な存在だ。となりの家のステレオがうるさい、犬に噛まれた、車ぶつけた、女房と別れたい(笑)、何かといえばすぐコートが登場するのがアメリカ社会。僕の友人のアメリカ人も、2人に1人くらいは何らかの形で裁判所のお世話になっている。(別にヤバイ友達が多いわけではありません。念の為)裁判所はアメリカ市民にとって身近な場所なのだ。 |
|
|
|
 |
そこで繰り広げられる人間ドラマはこれまた非常に生々しく奥が深い。欲望、陰謀、憎悪、悲嘆、人々が普段見せないナマの感情を思い切りぶつけあう法廷は、映画の格好の舞台となる。古くはモノクロ時代の傑作『十二人の怒れる男』('57)から『評決のとき』('96)まで、名作、傑作に事欠かない。
そんな中で、今年10月に公開されるや全米の話題をさらい、法廷ドラマの新たな金字塔となったのが、『ニューオリンズ・トライアル』だ。 |
| 「ニューオーリンズ・トライアル」の陪審員たち |
|
|
|
| ニューオーリンズの証券会社にリストラされた社員が押し入って銃を乱射、10人以上を射殺して自らも自殺を遂げる。この事件で犠牲になった社員の妻は、銃そのものの存在を許す社会にも責任の一端があると考え、犯罪に使われた銃を製造したメーカーを訴える。裁判の行方を握るのは、一般市民から選ばれた12人の陪審員たち。裁判で破れれば、倒産の危機さえある。なりふり構わぬ銃メーカーの首脳陣は、裁判コンサルタント、ランキン・フィッチ(ジーン・ハックマン)を雇い入れる。 |
|
|
|
あらゆる手段を使って陪審員を操作するフィッチと対決する弁護士のウェンドール・ローア(ダスティン・ホフマン)。そして、裁判のカギを握る謎の陪審員ニック・イースター(ジョン・キューザック)。
これ以上ふてぶてしい演技ができるだろうかというくらい憎たらしいジーン・ハックマン、追い詰められながらも必死に抵抗する役回りがやけに似合うダスティン・ホフマン、訳のわからん役をやらせればこの人の右に出るものがいない? ジョン・キューザック。これだけの演技派が揃ったら俄然期待が高まってしまう。 |
 |
ローアvs. フィッチ
「ニューオーリンズ・トライアル」より |
|
|
|
この映画、公開前からかなり人々の期待度が高かった。それというのも原作は人気作家ジョン・グリシャムの名作『陪審評決』(新潮文庫刊)。日本でもベストセラーになったので、読んだ人も多いだろう。プロットや人物描写がこれでもかという位練られていて緩慢な部分が少しもなく、一気呵成にラストまで読者を引っ張って行く。これほどのクォリティーの高い原作を映画化する場合、結果はたいてい大成功か大失敗のどちらかになる。全米の映画ファン達は興味津々で映画館に足を運んだのだが、結果はグッジョブ! 原作の面白さに拍車をかける演出で、ファンの期待に答える大ヒットとなったのである。
1月には日本で公開される『ニューオリンズ・トライアル』、サスペンス・ファンならずとも楽しめる映画だが、この映画を3倍面白くする方法がある。それはアメリカの法廷のしくみ、特に陪審員制度について知っておく事だ。 |
|
|
|
陪審員制度というとなにやら小難しく聞こえるけれど、実はとても単純な制度。一般市民の中から選ばれた12人が陪審員となり、被告の有罪無罪を投票で決めるシステムだ。彼らは別に法律の専門家ではなく、家庭の主婦や学生、職人、リタイヤした老人など、まったく普通の人ばかり。原告、被告双方の弁護士は、これらの人々を説得し、自分の側に一票を投じさせるべく必死の答弁を行う。
日本でも導入が検討されているこのシステム、アメリカという国を知る上でもとても参考になる。題して、「ニューオリンズ・トライアルを3倍楽しむ法」、来週、再来週に渡ってお送りします。何かむずかしそう、と思ってるそこのアナタ、騙されたと思って続きを読んでみてくださいませ。絶対面白いから! |
|
<<戻る
|