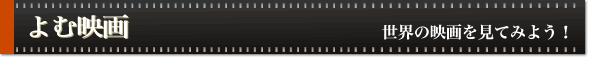|
【FILE35】フランス映画界の鬼才ジャン=クロード・ブリソー監督インタビュー
|
すべての女性に贈る、美しくも残酷な<性>の寓話『ひめごと』
|
ヌーヴェルヴァーグを生んだフランスの映画誌「カイエ・デュ・シネマ」のベスト10で、ペドロ・アルモドバルや宮崎駿を抑え、アッバス・キアロスタミの『10話』とともにベスト1を獲得したフランス映画界の鬼才ジャン=クロード・ブリソー監督の最新作『ひめごと』。美しくも残酷な<性>の寓話ともいうべきこの作品は、今まで映画ではほとんど描かれてこなかった女性のエロティシズムを真正面から描いています。果敢ともいえる試みのこの作品でブリソー監督が目指したものは何だったのか、本人に話を聞いてみました。
|
■ストーリー
|
 |
パリのクラブで働く若く美しいサンドリーヌはヌードダンサーのナタリーと出会い、意気投合した二人は共同生活を始める。ナタリーはサンドリーヌに、人生において快楽とSEXがいかに強力な武器になるかを教えた。そして自分たちの体を武器に、成功を手に入れる計画を立てる。まず一流企業に事務員として潜りこんだサンドリーヌは、社長の誠実な右腕で実力者のドラクロワへ接近する。ドラクロワはどんどんサンドリーヌとの関係に溺れていき、サンドリーヌはそれをゲームのように楽しむ。しかし、その関係にナタリーと社長の御曹司クリストフが思いがけない形で入りこみ……。 |
|
|
|
| ■<女性の性>をテーマにしたこの作品は、どこから着想されたのですか。 |
|
|
| 『甘い媚薬』という映画を撮っているときに、試しにエロティックなシーンを撮影したんですが、その時に女優が気持ち良さそうに演技をしていたんです。それを見て、ひょっとすると女性と性の関係を映画にできるのではないか、と思ったのが最初のきっかけでした。だから企画自体は6~7年前からあったんです。 |
|
|
| ■全編をとおしてエロティシズムを核に置きながら、リアリスティックな部分とファンタスティックな部分がうまく融合されているところが印象的でした。 |
|
|
| 私は現実主義や自然主義に興味がありません。いつも映画のなかに永遠性、時間に捕らわれていないもの――それがファンタスティックということになると思いますが――を加味したいと思っています。だからこのようにジャンルをミックスするわけで、私の作品ではいつも様々な要素が融合しています。今回の作品では、いろいろな要素のなかにエロティシズムを組み入れました。最初はロメールの『緑の光線』のような形式で、三人の女性の即興演出を考えていました。自由に性的なことを演じてもらったり、話してもらったりしようと。ただ、それは難しいということで、私が脚本を書くことになったんです。 |
 |
|
|
|
| ■女性二人が出会って肉体を武器に成功を手に入れようとする、というストーリーはどこから出てきたんですか。 |
|
|
私の日常生活の観察からです。今まで映画では、『赤と黒』のように男性の視点から描いた性の物語はありました。でも私が感心を持っているのは女性の性的な欲望です。だからこの作品では、今まで映画のなかで観られなかった性を描きたいと思ったんです。それと同時に、観客を退屈させない映画作りを目指しました。
物語に関してですが、私の母親はこの映画の主人公たちのように、成功するには性しか武器がないような階級の出身だったんです。だから普通の女の子がサクセスを夢見るというストーリーにしたんです。 |
|
|
| ■“セックス”は身近で誰の生活にもありながら、それゆえ軽んじられる側面もあると思います。あえて“セックス”をテーマにしたのはなぜですか。 |
|
|
 |
私がいつも考えるのは、何が一番人間を動かすかです。やはり人類の大きな原動力はセックスだと思います。権力やお金は二次的について来るものです。この作品でも、人間の行動体系のなかで成功と愛とお金と権力では何が一番ほしいかを考えて、二人のヒロインは権力を求めていることにしたんです。だからセックスによって権力を求めるという映画を作ろうと考えました。彼女たちは愛を求めていません。彼女たちにとって愛は、依存してしまえば成功を妨げるものです。彼女たちは成功のためにセックスを使いますが、私の日常で登場人物のモデルになる人たちがいました。 |
|
|
|
| ■この作品は時間とともに、その空気や雰囲気が変わっていきますが。 |
|
|
| 私がこの映画のなかで特に重視したのは、三つの部分です。最初の45分間は二人の女性が出会い、そこで欲望や快楽の追求を見せます。実はこれが残りの1時間10分を決定づけるのです。その次にオフィスでの彼女たちのエロティックな生活があり、最後にこの映画の本当のテーマが、クリストフという男の登場とともに表出します。そうなるようにこの映画は作られているのです。 |
|
|
| ■クリストフが登場してからこの作品の本当のテーマが出てくるという構成は、最初から考えていたんですか。 |
|
|
| いいえ、違います。第三部にあたる本当のテーマは脚本を書きながら思いついたことで、最初からあったわけではありません。いつもそうですが、前もってどういう結論になるかわからずにシナリオを書き出すんです。だから本当に自分がシナリオを書き上げることができるかどうか、いつも不安です。この作品を撮り終えたときも、本当に自分が撮ったのかと驚いたぐらいです。 |
|
|
| ■サンドリーヌとナタリーはエロティックというよりむしろすごく無邪気で、まるで小さい子供がじゃれ合う感じでした。ヒロインの女優二人を選んだ理由は何ですか。 |
|
|
今回に限らず、女優を選ぶのにとても重要なことは、どんなにエロティックなシーンの演技でも品位があるということです。マリリン・モンローやブリジット・バルドーのような外見がセクシュアルな女性を私は望んでいません。普通の女性がいいんです。それと同時に、この女性の裸を見たいと観客に思わせる魅力もなければなりません。ナタリーを演じたコラリー・ルヴェルは以前からよく知っていましたし、彼女には優美さや気品があります。この映画ではサンドリーヌがヒロインになっていますが、実は物語の中心人物はナタリーなんです。
サンドリーヌ役のサブリナ・セヴクに関しては、“フリをする”演技ができる女優を選ぶのが今回のキャスティングの重要なポイントでした。彼女が演じたなかで一番重要なシーンは自慰行為をする場面です。相手が女性でも男性でも、その人がフリをしているのかいないのかを見分けるのはほとんど不可能です。だからこれは嘘の原型ともいえます。 |
 |
|
|
|
| ■全体にサスペンスを思わせる作りが作品の印象とは別に、エンターテインメント性を感じさせていたと思います。 |
|
|
| 観客の頭のなかで想像が膨らんでいくような映画を作りたいと思ったんです。例えば、オフィスのなかでサンドリーヌがブラジャーとパンティを脱いで、廊下で男性社員と話すシーンがあります。そのときドラクロワは嫉妬心に駆られて欲望も感じています。ひょっとしたら、そういうことは日常で頻繁に起こっているかもしれないわけです。だから想像はどんどん膨らむもので、そこにこそ、私は興味がありました。サンドリーヌとナタリーが一緒にトイレの方に行くと、例え何もなくても“もしかしたら二人はセックスをしているのではないか”と想像が膨らんでいく。そういう映画を撮りたいと思ったんです。 |
|
|
| ■「フリをする」という演技といい、主人公二人が登場人物と同時に観客にも見られていることといい、映画自体が二重の構造になっていますね。 |
|
|
 |
二重構造というのは間違いではないですが、この作品はもっと複雑な構造になっています。例えばドラクロワという人物はサンドリーヌに恋焦がれますが、そこには彼女がすべて演技をしていたという構造があります。ナタリーも実はクリストフに操作されていた。その状況でサンドリーヌに近づいたわけですから、ナタリーも演技をしていたことになる。それをさかのぼって考えると、面接のシーンで長い廊下に女性が並んで座っています。その端でサンドリーヌとナタリーが待っていると、ナタリーだけが呼ばれます。でもよくよく考えると、クリストフがそうなるように仕向けていたことになる。
この映画はすべてが嘘なんです。すべてが<虚>でできているんです。では何が真実かといわれれば、それはラストのシーンです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<<戻る
|